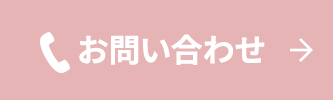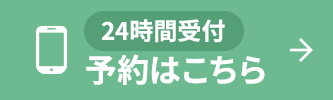じんましん(蕁麻疹)とは

じんましん(蕁麻疹)蕁麻疹は、突然皮膚が赤く盛り上がり、強いかゆみを伴う症状が特徴的な皮膚疾患です。一度症状が出ても、しばらくすると自然に消えてしまうことが多く、同じ場所に再発することもあれば、別の部位に現れることもあります。特定の部位だけに発生する場合もあれば、全身に広がるケースもあります。
一般的に、じんましん(蕁麻疹)はアレルギーによって引き起こされると思われがちですが、実際にはアレルギー以外の要因によって発症することも多く、原因が特定できないケースも少なくありません。一過性のじんましん(蕁麻疹)であれば、自然に治ることがほとんどですが、症状が1か月以上続く場合は「慢性蕁麻疹」と診断され、治療が必要になることがあります。
また、じんましん(蕁麻疹)が突然発症し、息苦しさや吐き気、下痢などの症状を伴う場合は、アナフィラキシーショックの可能性があり、迅速な対応が求められます。重篤な症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診し、必要に応じて救急搬送を検討することが重要です。
じんましんの症状
 じんましん(蕁麻疹)の症状は、突然皮膚に赤みが出現し、盛り上がった膨疹ができることが特徴です。多くの場合、かゆみを伴いますが、人によってはほとんどかゆみを感じないこともあります。また、チクチクした痛みを感じることもあり、症状の感じ方には個人差があります。
じんましん(蕁麻疹)の症状は、突然皮膚に赤みが出現し、盛り上がった膨疹ができることが特徴です。多くの場合、かゆみを伴いますが、人によってはほとんどかゆみを感じないこともあります。また、チクチクした痛みを感じることもあり、症状の感じ方には個人差があります。
膨疹は円形や楕円形で現れることが多いですが、衣類の摩擦や圧迫が原因となる場合は、線状に発症することもあります。大きさは数ミリ程度のものから、複数の膨疹が融合して広範囲に広がるケースもあり、場合によっては10cm以上の大きさになることもあります。
症状が現れるタイミングもさまざまで、特定の時間帯に繰り返し発症することもあれば、入浴後や運動後などの特定の状況で発症することもあります。まれに、皮膚だけでなく内臓に反応が起こることがあり、消化管に炎症が及ぶと、吐き気や下痢、腹痛といった症状が現れることもあります。
じんましんの診断・検査
診断
蕁麻疹の診断では、まず問診で発症の経緯や生活習慣、服用している薬、アレルギー歴などを詳しく伺います。その後、皮膚の状態を視診・触診することで診断を行います。
じんましん(蕁麻疹)は、大きく分けて「原因が特定できるもの」と「原因が不明なもの」に分類されます。アレルギーや寒暖差、日光など、特定の要因によって引き起こされる場合は、血液検査やアレルギー検査を行い、原因物質を特定することがあります。ただし、約7割のケースでは明確な原因が特定できず、症状の出方から診断を下すことが一般的です。
じんましん(蕁麻疹)の発疹は、赤みがありながらも皮膚表面にじくじくとした湿り気がなく、短時間で自然に消失することが特徴です。他の皮膚疾患と区別しやすい点でもあり、この特徴をもとに診断が行われます。
じんましん(蕁麻疹)検査
内臓の病気が関与している可能性がある場合には、血液検査を実施し、肝機能や腎機能、白血球数などを調べることがあります。必要に応じて、皮膚のパッチテストやアレルギー検査を行うことで、より詳細な診断を行います。
じんましんの治療方法
治療薬
じんましん(蕁麻疹)は、皮膚の深い層である真皮層に炎症が起こるため、表面に塗るタイプのかゆみ止めでは十分な効果が得られません。そのため、治療の中心となるのは、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服による治療です。
一時的な蕁麻疹であれば、症状が自然に消失することもありますが、慢性的に繰り返す場合には、一定期間の服薬を継続することで症状を抑えることが可能です。
かゆみが強い場合や症状が重い場合には、抗アレルギー薬とともに、症状を抑えるための補助的な薬を使用することもあります。
ヒスタミン薬について
蕁麻疹の治療に用いられる抗ヒスタミン薬は、皮膚に炎症を引き起こすヒスタミンの働きを抑える効果があります。ただし、一部の抗ヒスタミン薬には眠気を伴う副作用があるため、服用後の自動車やバイクの運転、精密作業には注意が必要です。
市販の風邪薬やアレルギー薬で眠気を感じることがある方は、抗ヒスタミン薬の影響を受けやすい可能性があります。そのため、日常生活で運転や機械操作を行う機会が多い方は、眠気の少ないタイプの薬や、就寝前に服用する薬を選択することができます。
医師と相談の上、患者さんの生活スタイルに合った薬を選ぶことが大切です。