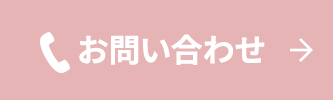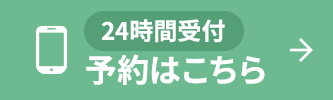たこ・魚の目とは
 たこや魚の目は、皮膚が繰り返し圧迫や摩擦を受けることで、部分的に角質が厚くなり形成される皮膚疾患です。医学的には「たこ」を胼胝(べんち)、「魚の目」を鶏眼(けいがん)と呼びます。たこは広範囲に角質が増殖するのに対し、魚の目は中心に芯ができ、痛みを伴うことが特徴です。どちらも主に足に生じますが、ペンだこや座りだこなど、手やその他の部位にも発生することがあります。
たこや魚の目は、皮膚が繰り返し圧迫や摩擦を受けることで、部分的に角質が厚くなり形成される皮膚疾患です。医学的には「たこ」を胼胝(べんち)、「魚の目」を鶏眼(けいがん)と呼びます。たこは広範囲に角質が増殖するのに対し、魚の目は中心に芯ができ、痛みを伴うことが特徴です。どちらも主に足に生じますが、ペンだこや座りだこなど、手やその他の部位にも発生することがあります。
たこ・魚の目の症状
たこは、足の裏や手のひらなど、圧力がかかる部位に広範囲で角質が厚くなる状態です。基本的には痛みを伴わず、肌を保護するために自然に形成されます。しかし、放置すると硬くなり、違和感を覚えることがあります。たとえば、筆記時にできる「ペンだこ」や、正座をする習慣のある人にできる「座りだこ」も同じ原理で発生します。
一方で、魚の目は厚くなった角質の一部が芯のようになり、皮膚の深部へと食い込んでいくため、歩行時や圧迫時に強い痛みを引き起こします。特に足の裏や指の付け根などにできやすく、患部が炎症を起こすと、赤みや腫れを伴うこともあります。また、糖尿病を持つ方では痛みを感じにくく、感染が進行しやすいため注意が必要です。
たこ・魚の目の診断
たこや魚の目は、ウイルス性のイボ(尋常性疣贅)と見た目が似ているため、自己判断が難しいことがあります。尋常性疣贅は、表面に小さな黒い点が見られるのが特徴で、治療法も異なります。さらに、まれに皮膚腫瘍がたこや魚の目と誤認されることもあるため、症状が長引いたり、変化が見られたりする場合は、皮膚科での診察を受けることが重要です。
たこ・魚の目の治療
たこや魚の目は、一度治療をしても、原因となる圧迫や摩擦が続く限り再発する可能性があります。そのため、根本的な対策として、歩き方の矯正や適切な靴の選択、フットケアの継続が必要です。
圧迫や摩擦を避ける
たこや魚の目の発生を防ぐためには、日常生活での圧力や摩擦を軽減することが大切です。特に足に合わない靴を履いている場合、足の特定の部位に負担がかかりやすくなります。インソール(中敷き)を活用し、足への負担を均等に分散させることで、症状の悪化を防ぐことができます。また、歩き方に癖がある場合は、専門的な指導を受けて矯正することも有効です。
削る
皮膚科では、たこや魚の目に対して、専用のメスやハサミを使用して厚くなった角質を削る治療を行います。特に魚の目は、芯が皮膚の奥深くまで入り込むことが多いため、芯を取り除くことで痛みが軽減します。ただし、長期間放置したものは、除去後もしばらく違和感が残ることがあります。
塗り薬・貼り薬
角質を柔らかくするための外用薬を使用することで、角質の硬化を抑えたり、除去しやすくしたりする効果が期待できます。貼り薬は一定期間貼り続けることで、徐々に魚の目の芯を軟化させることが可能です。治療法は患者さんの症状やライフスタイルに応じて選択できますので、医師と相談しながら適切な方法を決めることが大切です。