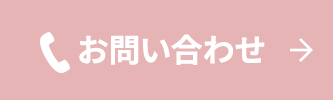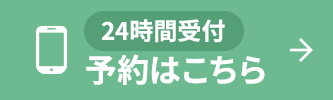水虫について

水虫は、白癬菌と呼ばれる真菌(カビ)の一種が皮膚に感染して起こる皮膚真菌症です。白癬の感染部位によって、足白癬、手白癬、爪白癬、体部白癬、股部白癬などに分類されます。その中でも最も一般的なのが足白癬で、日本人の約2割が発症しているとされています。白癬菌は、公衆浴場、プール、スポーツ施設、家庭内、老人ホームや介護施設など、人が裸足で過ごす場所を介して感染することが多く、また革靴や厚手の靴下によって蒸れた環境も菌の増殖を助ける要因となります。小さな傷口から菌が入り込むこともあり、一度感染すると治療を怠ることで手白癬や爪白癬へと広がる可能性もあります。
白癬の症状
足白癬
足白癬は「趾間型」「角質増殖型」「小水疱型」の3種類に分類され、それぞれ異なる特徴を持っています。
趾間型
足の指の間が湿気によってジュクジュクとただれたり、乾燥して皮むけが起こるタイプです。亀裂や赤みが生じ、かゆみを伴うこともあります。
角質増殖型
かかとを中心に足の裏全体の角質が厚くなり、硬くなるタイプです。かゆみがほとんどないため気づきにくく、長期間放置されやすい特徴があります。
小水疱型
足の裏や側面に小さな水ぶくれができるタイプで、かゆみを伴うことがあります。水ぶくれが破れると、皮むけや赤みが生じることもあります。
手白癬
手のひらや指に発症し、皮がむけて厚くなったり、赤みや水ぶくれができることがあります。足白癬と同様に、角質が硬くなることもあり、治療が遅れると爪白癬へ進行することもあります。
爪白癬
爪に感染すると、爪が白く濁ったり厚くなったりして、変形や脆弱化が起こります。進行すると爪がもろく崩れやすくなり、日常生活に支障をきたすこともあります。特に親指に発症しやすい傾向がありますが、放置すると他の爪にも広がることがあります。
股部白癬・体部白癬
股や太ももの内側、体の他の部位にも感染が広がることがあります。円形に広がる赤みや皮むけ、水ぶくれが特徴で、強いかゆみを伴うことが多いです。特にスポーツをする人やペットを飼っている人は、感染リスクが高くなる傾向があります。
水虫(白癬)の検査
 白癬の診断には、感染部位の角質や水ぶくれ、剥がれた皮膚、爪の一部を採取し、顕微鏡で白癬菌の有無を確認する検査が行われます。検査自体は短時間で完了し、5分程度で結果が判明します。自己判断で市販の水虫薬を使用している場合、検査で菌が検出されにくくなるため、診察前の2週間程度は使用を控えることが推奨されます。
白癬の診断には、感染部位の角質や水ぶくれ、剥がれた皮膚、爪の一部を採取し、顕微鏡で白癬菌の有無を確認する検査が行われます。検査自体は短時間で完了し、5分程度で結果が判明します。自己判断で市販の水虫薬を使用している場合、検査で菌が検出されにくくなるため、診察前の2週間程度は使用を控えることが推奨されます。
水虫(白癬)の治療
塗り薬
軽度の水虫の場合、抗真菌成分の外用薬を使用して治療を行います。かゆみや炎症が強い場合には、一時的にステロイド剤を併用することもありますが、長期的な使用は避ける必要があります。
飲み薬
爪白癬や角質が厚くなった白癬には、外用薬では十分な効果が得られないことが多く、抗真菌薬の内服治療が必要になることがあります。ただし、抗真菌薬は肝臓に負担をかける可能性があるため、定期的な血液検査を行いながら慎重に服用する必要があります。また、抗精神病薬や抗うつ薬を服用している場合には、薬の相互作用の問題から処方が難しいことがあるため、事前に医師と相談することが重要です。